Shippio様が切り拓く貿易DXの新常識。「舵を取ろう、明日に向かって。」
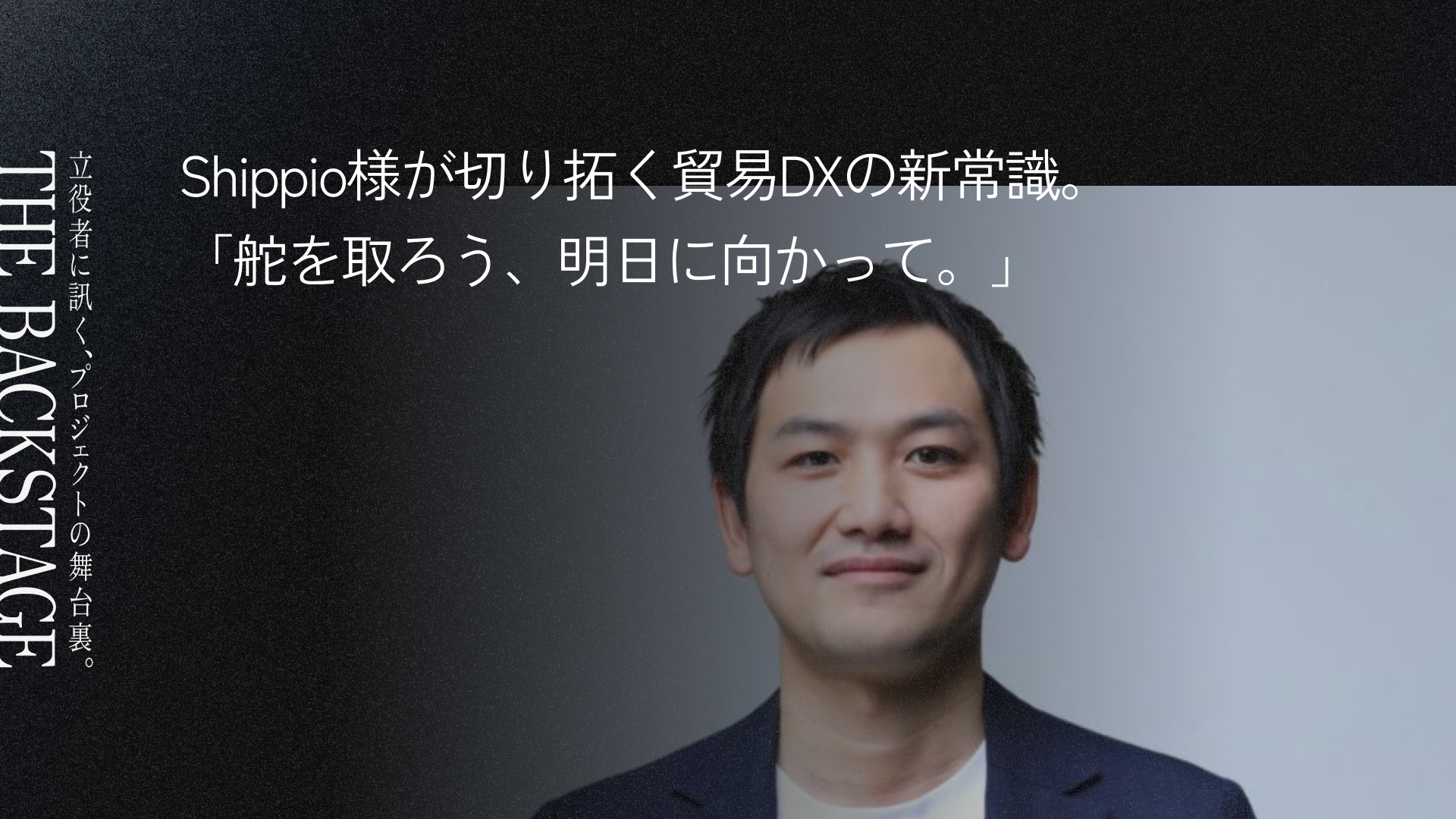
デジタル化が進む現代でも、貿易業界では、人の手を介した丁寧な業務が今なお信頼を支えています。しかし、船会社、倉庫、通関…多くの関係者との連携は、時に煩雑さを極め、効率化は長年の課題でした。
そんな業界の”当たり前”に新しい風を吹き込むのが、「日本初のデジタルフォワーダー」株式会社Shippio様(以下、Shippio)です。
テクノロジーの力で貿易業務の変革に挑み、業界全体のDX(Digital Transformation)と産業変革を指す IX (Industrial Transformation)を推進しようとしているShippio。長年培われてきた実務の知恵と、最新テクノロジーの融合ーーその先に、どのような未来が待っているのでしょうか。
今回、Shippioの挑戦の裏側と、未来への熱き想いに迫るべく、VP of HR (人事部門責任者) の伊達 雄介 様、VP of Corporate Planning / VP of Operation (経営企画部門/オペレーション部門責任者) の井上 裕史 様、Director of Product (プロダクト開発部門責任者) の伊井 壮太郎 様にお話を伺いました。
1.「当たり前」を変える挑戦。デジタルフォワーダーとは?
古くからの商慣習が残る貿易業界に、革新の風を吹き込むShippio。彼らが取り組む「デジタルフォワーディング」とは一体何なのか、その核心に迫ります。
ー Shippioが取り組む「デジタルフォワーディング」の意義を教えてください。
伊達様:
まず、「フォワーダー」とは、貿易における輸出入手続きを荷主に代わって管理・代行する役割を担う事業者です。輸送、通関、倉庫管理、金融・保険など、多くの関係者との調整を行いながら貿易を成立させます。
この事業は従来から存在しますが、依然として電話、メール、ファックス、エクセルなどを活用したアナログな運用が主流です。そこでShippioは、フォワーディング業務全体をデジタル化し、業務の効率化と標準化を推進 するデジタルフォワーディングを事業として展開しています。業務のオペレーションをクラウドに集約することで、煩雑な業務プロセスを抜本的に変革しています。
ー デジタルフォワーディングがもたらす変革とは、どういったものなのでしょうか?
伊達様:
フォワーディング業務そのものは従来からあるものですが、そのやり方を根本から見直し、DXを進めるのが「デジタルフォワーディング」です。Shippioは、デジタルフォワーディングサービス「Shippio Forwarding」を進める中で培ったクラウド技術を、SaaSプロダクト 「Shippio Cargo」や「Shippio Works」 として展開しています。単なる業務効率化にとどまらず、国際物流業界全体の新たな標準を構築することを目指しています。最終的には、貿易プラットフォームを確立し、業務のすべてがオンラインで完結し、蓄積された貿易データを経営の武器として活用される未来 を実現したいと考えています。
ー これらのサービスの独自性や強みを教えてください。
伊達様:
国際物流に関する業務はアナログで労働集約的な部分が多いため、業界の皆さん自身にも課題感はあります。一方で現在の業務も蓄積された知見の上で成り立っているものでもあり、「課題を感じながらも、変えることも難しい」というジレンマを抱えています。しかし、労働人口の減少が進む中、DXの必要性は避けられません。Shippioの強みは、自分たち自身がフォワーダーとして実務のDXを推進している点にあります。M&Aでグループとなった通関事業者の業務のデジタル化にも着手し、先々はそのノウハウを業界全体に展開することで、変革を促進していきたいと思っています。単なるシステム開発ではなく、現場の課題を深く理解し、業界の新たな標準を生み出し根付かせていくことが、Shippioの使命です。
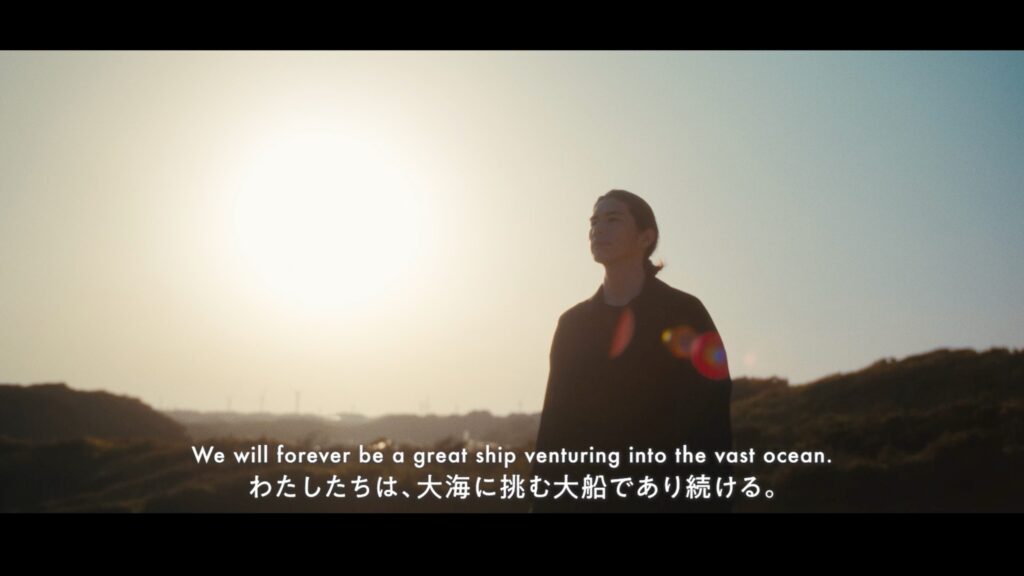
2. 業界の「常識」に挑む。DX推進の壁と、Shippioの突破力
DXの必要性は理解しつつも、進まない背景には何があるのか。どのようにその課題を乗り越えようとしているのか、伺いました。
ーDXの必要性は理解されている一方で、浸透が進まない理由は何だとお考えですか?
伊達様:
最大の理由は、単純に「誰も切り込まなかったから」です。既存の業務が最適だと考えている人は、おそらくほとんどいません。多くの人が「この業務はもっといいやり方があるはずだ」と感じています。しかし、それを変えるためにコストをかけるという判断には至っていないのが現実です。その背景には、貿易やサプライチェーンが「コストセンター」として扱われていることがあります。例えば、営業向けのSaaSは売上に直結するため、システム投資の優先度が高く、Salesforceのようなサービスが普及しています。一方で、物流や貿易のオペレーション部分については、基本的にコスト削減が重視されるため、新たな投資が後回しにされがちです。DXの必要性を理解していても、「現状の業務で何とか回っているのだから、一旦はこのまま続けよう」という意識が強く、新しい仕組みやシステムの導入に踏み切れない企業が多いのです。
ー そういった前提がある中で取り組みを続けられているShippioが、現在直面している最大の壁はありますか?
伊達様:
業界全体が課題と感じているにもかかわらず、DX推進のモメンタムがまだ生まれていないことが、私たちが直面している最大の壁です。多くの企業はDXに関心を持っていても、具体的なシステム投資に踏み切るまでには至っていません。そのため、Shippioがやるべきことは、単なるソリューションの提供ではなく、「DXを実現するための流れそのものを業界内に作り出すこと」 だと考えています。このモメンタムを生み出せるかどうかが、今の私たちの最大のチャレンジですね。経済産業省が、「貿易プラットフォームを通じてデジタル化される貿易取引の割合を、2028年度までに10%に」という定量目標を掲げるなど、着実にそのモメンタムは生まれ始めていることを感じています。
3. 社内外を巻き込む「共感」の創造。映像制作プロジェクトの舞台裏
社内外にShippioのビジョンを伝え、共感を呼ぶために制作された映像。そのプロジェクトの背景には、どのような想いがあったのでしょうか。
ー今回、どのような思いがあって映像制作に踏み切られたのでしょうか。
伊達様:
映像制作を決めたのは約1年前です。私たちの取り組んでいるドメインでは、事業のサイクルが比較的ゆっくり進むため、受注がすぐに積み上がるような、わかりやすい成長の指標を示しにくい領域です。そのため、社内では「本当にこの方向でいいのか」「私たちはどこを目指しているのか」といった声が定期的に上がっていました。もちろん、言葉で説明することも重要ですが、映像やビジュアルで見せることで、より理解しやすく、純粋にワクワクしてもらえるのではないかと考えました。映像を使って、社内のモメンタムを向上させ、その起点にすることが狙いでした。
加えて、このプロジェクトがスタートしたのは2024年の3月頃だったのですが、同年5月にはShippio主催の「ロジスティクスDXサミット」が開催される予定でした。このイベントでは、国際物流や貿易の未来や各社の取り組みについて、5つのテーマで講演を行うことになっていたのですが、サプライチェーンや貿易に関わる多くの方々が参加するため、その場でビジョンムービーとして活用することで、Shippioの目指す未来を伝える効果的なツールになると考えました。
ーGEKIを選ばれたきっかけを教えてください。
伊達様:
GEKIの作左部さんとは以前からの知り合いでしたが、最初から決めていたわけではなく、3社ほどに声をかけました。その中で、最終的にGEKIに決定したのは、短納期の要望に応えられる柔軟性と、コミュニケーションを通じて生まれた信頼感 でした。カンファレンスの開催が5月後半だったため、5月初旬までに制作を完了させる必要がありました。約2ヶ月以内という厳しいスケジュールでしたが、実現可能だと応えてくれたのは、GEKIだけでした。また、仮に他の2社もスケジュール面で対応できたとしても、やり取りを通じて感じたGEKIのクリエイティブに対する姿勢や理解度が決め手となり、最終的に依頼を決めました。
ー映像を通して伝えたかったメッセージを教えてください。
伊達様:
この映像はお客様にもご覧いただくものだったため、共感してもらえる内容にすることが重要でした。また、お客様自身や、お客様がこれまで築いてこられたものに対して、Shippioとしてリスペクトを示すことも大切な要件でした。ただし、それは迎合するという意味ではありません。Shippioでは、「業界やお客様に対する敬意を忘れない」という姿勢を大切にしています。そのため、単にイノベーションや破壊的変革(ディスラプト)を打ち出すのではなく、これまでの積み上げを尊重しながら、どのように業界を一緒にアップデートしていけるか というメッセージを込めました。もうひとつ意識したのは、「スケール感」です。私たちの事業は、個々の企業にとっての効率化に留まらず、業界全体の変革につながるものです。「業務のDXを進めています」という身近な話ではなく、国際物流全体の未来を描く壮大なビジョン を伝えたかったのです。
ーこのプロジェクトにおいて期待された部分があれば教えてください。
伊達様:
GEKIさんと初めて打ち合わせをした際、GEKI代表の作左部さんが独立前に、国際物流や貿易領域の支援を経験されており、業界への理解があることは安心感につながりました。また、「クリエイティブはあくまで手段」 という共通認識を持てたことが、非常に大きかったです。「映像を使って何を解決するのか?」という議論を、発注前から重ねることができたのも大きかったですね。単に映像作品を作るのではなく、Shippioが抱える課題を解決するための議論ができたことで、GEKIとの信頼関係が強まりました。プロジェクトが始まってからも、そのスタンスは変わらず、一緒に考えてくれるパートナーとして、非常に期待を持って取り組めました。
4.「舵を取ろう、明日に向かって。」に込めた想い
キーメッセージ「舵を取ろう、明日に向かって。」に込められた想いと、Shippioが目指す、物流の未来の姿を紐解きます。
ー完成した映像は、当初のイメージ通りのものになりましたか? また、ストーリーテリングの手法を採用した理由について教えてください。
伊達様:
最終的には期待通りの映像になりましたが、制作の過程では「プロダクトの解像度を上げる方向にするか、それともコンセプトを重視するか」で大きく悩みました。初めは、Shippioのプロダクトが業界をどう変革するのか、具体的なDXの影響を見せる案もありました。しかし、議論を重ねる中で、「まずはShippioの目指す世界観を伝えることが優先ではないか」という結論に至り、コンセプトを軸とした映像に舵を切りました。また、最終的に擬人化とストーリーテリングを採用したのは、ある意味「消去法」的な側面もあります。私たち自身がまだ、プロダクトの具体的な機能や状態を言語化している途上であるため、現時点では具体的な機能よりもShippioのビジョンを明確に伝えることが重要だと判断しました。DXの本質は技術だけではなく、「何を目指して変革を起こすのか」が明確でなければ意味がありません。今回の映像は、そのビジョンを形にすることを最優先にしたものです。
ーカンファレンスで初披露された映像に対し、社内外からどのような反応がありましたか?
伊井様:
傾向としてあったのは、物流出身の方々からの評判が良かった、ということです。私たちの会社は、物流とプロダクト開発の両方を手掛ける、ITと物流のハイブリッドな企業です。物流は、「昨日と同じ明日を作ることに価値がある」という世界観が強いのですが、映像では、その世界観を尊重しながらも新しいものを創り出す、というコンセプトを明確に打ち出しました。その点が、彼らにとってインパクトが強かったのではないかと思います。
ー映像にある「舵を取ろう、明日に向かって。」というメッセージに込められた想いについて、お聞かせください。
伊達様:
映像のメッセージには、「Shippioとしての当事者意識を高める」という意図が込められています。物流業界では、伊井も話しした通り「昨日と同じ今日、今日と同じ明日」を作り続けることが価値とされ、変化はむしろリスクと捉えられがちです。しかし、私たちはその常識を打ち破り、「今日と違う明日をどう創るか」という視点を持って業界を変革していく必要があると考えています。このメッセージを言葉として形にしていく上で、中心的な役割を担ったのが井上です。彼は社歴が最も長く、オペレーション部門の責任者として現場を熟知しているだけでなく、M&Aした通関事業者の社長も兼務しており、物流業界への深い理解を持っています。
映像に込めるメッセージを設計するにあたり、井上は「業界へのリスペクトを忘れずに、どのような表現が最適か」を細部までこだわり抜きました。GEKIさんから提案されたスクリプト案に対しても、単なる表現の調整ではなく、「この言葉はこうあるべき」「あえてひらがなや漢字にするべき」といった言葉のニュアンスまで徹底的に精査しました。Shippioが物流業界の変革をリードするという決意と、業界全体とともに未来を創り上げるという姿勢が、このメッセージには込められています。
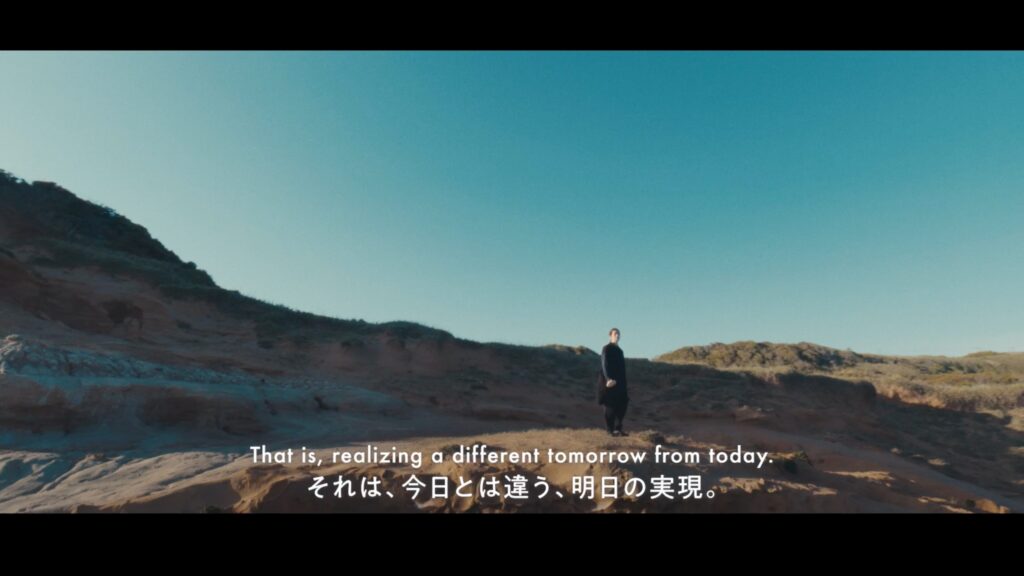
ー井上さんは、この映像がブランド価値にどのように寄与していると思われますか?
井上様:
社外向けには、定量的なデータはまだ取得できていませんが、社内では確実に変化がありました。物流業界出身でShippioにジョインしたメンバーの目線が揃い、「私たちは何のためにこの事業をしているのか」 という共通認識を持つことができた点は、ブランドとして大きな価値があったと考えています。
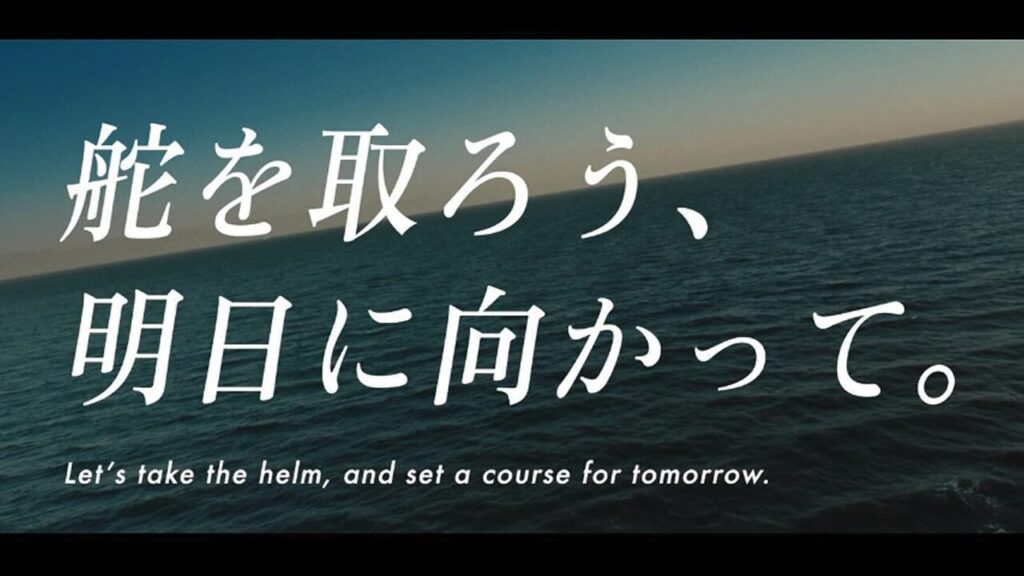
5. 産業の転換点をつくるーーShippioが目指す、歴史に刻まれるTransformation
壮大なミッションを掲げるShippio。彼らが目指す未来とはどのようなものなのでしょうか。
ーShippioが掲げるミッション「産業の転換点をつくる」。これは、100年に1度レベルの「産業の変革」を意味します。業界のDX推進がミッション実現にどうつながるのでしょうか?
伊達様:
日本は島国であり、貿易は経済活動や人々の生活に不可欠な社会的インフラです。Shippio Platform の拡大を通じて貿易や国際物流業界のDXを進めることで、インフラの持続性を高めるだけでなく、この業界で働く人々がデジタル技術を活用して役割やスキルを高度化し、価値の幅を広げていく。すなわち、少ない時間でより高い付加価値を提供できる「アドバンスト」な人材に転換し、将来のキャリアも拓けていく世界を実現したいと考えています。国際物流業界やそこで働く人々のキャリアがアドバンストになったその先に、貿易が支えるあらゆる「産業」を捉え、産業そのものを転換することを目指しています。
ー今後、企業として定着させたい文化と、伝えたいメッセージを教えてください。
井上様:
映像の最後にもあるように、私たちが伝えたいのは「昨日と違う明日を創る」という意識です。これまでの物流業界は、「昨日と同じ明日を確実に再現する」ことが重視されてきました。しかし、少しずつでも変化を起こし、効率化を進めることが、より良い未来につながると考えています。一朝一夕に変えられる業界ではありませんが、「昨日より今日が少しでも良くなった」という積み重ねが、理想に近づくための唯一の道だと思います。
伊達様:
例えば、現在ではZoomやGoogleのクラウドツールを使った働き方が当たり前になっています。しかし、5年前のコロナ禍以前は、パソコンを使ったオンライン会議は一般的ではありませんでした。今では、ほとんどの人がスマートフォンを持ち、クラウドツールを活用することが標準化されています。私たちが目指すのは、貿易や国際物流の業界でも、同じように「Shippioのプラットフォームを使うことが当たり前」な未来を創ることです。Shippioが業務の標準ツールとして溶け込んでいる未来を実現することが、私たちの目指す姿です。
長年の課題を抱える貿易業界に変革をもたらそうとするShippio。
デジタルフォワーダーとしての独自の取り組み、そして未来への熱い想い。
彼らの挑戦は、日本、そして世界の物流の「当たり前」を、大きく変えようとしています。





